この記事の目次
「ステーブルコイン」という言葉をニュースなどで耳にする機会が増えていませんか?「ビットコインと同じ暗号資産(仮想通貨)でしょ?」と思うかもしれませんが、実は全く異なる特徴を持つ、次世代のデジタル通貨です。
ビットコインなどの暗号資産は価格変動が非常に大きい一方、ステーブルコインは「安定した(Stable)」という名の通り、日本円や米ドルなどの法定通貨と価値が連動するように設計されています。
そして今、日本で特に注目を集めているのが、1コイン≒1円の価値を持つ「JPYC」です。2023年6月に施行された改正資金決済法のもと、JPYC株式会社は2025年8月に国内で初めて「資金移動業者」として登録され、同年秋から本格的に円建てステーブルコインを発行することが発表されました。
この記事では、投資初心者の方にも分かりやすく、以下の点を解説していきます。
- そもそもステーブルコインとは何か?
- 日本円ステーブルコイン「JPYC」のすごいところ
- 金融庁に認可されたことで、何が変わるのか?
- 私たちの生活にどう影響し、どんな未来が待っているのか?
そもそもステーブルコインとは?3つの種類と仕組みを解説
まずは基本から押さえましょう。ステーブルコインは、暗号資産の「ブロックチェーン技術による送金の速さ・安さ」と、法定通貨の「価値の安定性」を両立させた、いわば“良いとこ取り”のデジタル通貨です。この価値の安定は、主に3つの仕組み(モデル)によって支えられています。
価値を支える3つの仕組み
- 法定通貨担保型(JPYCはこれ!)
仕組み: 発行されるコインの価値と同額の法定通貨(円やドルなど)を、発行者が銀行預金などで保管します。最もシンプルで信頼性が高いモデルです。
代表例: JPYC、USDC、USDT - 暗号資産(仮想通貨)担保型
仕組み: ビットコインやイーサリアムといった他の暗号資産を担保にします。価格変動リスクに備え、発行額以上の暗号資産を担保に入れる「過剰担保」が一般的です。
代表例: DAI - アルゴリズム型(無担保型)
仕組み: 担保資産を持たず、プログラム(アルゴリズム)がコインの供給量を自動で調整し、価格を一定に保とうとします。
注意点: 過去にTerraUSD(UST)が暴落した事例があり、仕組みの脆弱性が指摘されています。
このように、ステーブルコインと一言で言っても、その信頼性の源泉は異なります。JPYCが採用する「法定通貨担保型」は、最も安全性が高い仕組みとして広く認識されています。
日本初の円建てステーブルコイン「JPYC」の特徴
JPYCは、JPYC株式会社が発行する、常に1 JPYC = 1円で取引されることを目指すステーブルコインです。その最大の特徴は、日本の法律に準拠し、金融庁の監督下で運営される点にあります。
これまでの歩み:プリペイドから「電子決済手段」へ
JPYCはもともと、法律上「前払式支払手段」として発行されていました。これはSuicaや楽天Edyのような電子マネーに近い扱いです。
しかし、2023年6月の改正資金決済法の施行により、ステーブルコインは新たに「電子決済手段」として法的に定義されました。これを受け、JPYC株式会社は2025年8月に資金移動業者として登録。これにより、JPYCは単なるプリペイドではなく、送金や決済に幅広く使える、法律で認められたデジタル通貨へと進化を遂げたのです。
JPYCとPayPayの違いは?
同じ「資金移動業者」であるPayPayとは何が違うのでしょうか?以下の表で比較してみましょう。
| 比較項目 | JPYC(ステーブルコイン) | PayPay |
|---|---|---|
| 法的分類 | 電子決済手段 | 資金移動業に基づくサービス |
| 技術基盤 | ブロックチェーン上のトークン | 中央集権的なデータベースシステム |
| 主な用途 | 国際送金、企業間決済、Web3サービス | 日常の買い物、個人間送金 |
| 海外送金 | 可能 | 不可能 |
| 消費者保護 | 誤送信時の補償なし | 規約に基づく補償制度あり |
(出典: 提供資料を基に作成)
一番の違いは技術基盤です。ブロックチェーンを基盤とするJPYCは、銀行などを介さずに世界中の相手に直接、安く、速く送金できるという大きなメリットがあります。
金融庁認可でどう変わる?JPYCのメリットと注意点
資金移動業者として正式に認可されたことで、JPYCの可能性は大きく広がります。
メリット①:送金・決済がもっと自由に、安く、速く
- 国際送金: 従来、数千円の手数料と数日かかっていた海外送金が、ほぼゼロに近い手数料で、数分で完了する可能性があります。
- 企業間決済(B2B): 24時間365日、リアルタイムでの決済が可能になり、企業の資金繰り改善に貢献します。
メリット②:Web3サービスでの活用が本格化
- NFTの売買: NFTマーケットプレイスでの支払いが、暗号資産の価格変動を気にすることなく、日本円感覚で行えるようになります。
- DeFi(分散型金融): ステーブルコインを貸し出したり預け入れたりすることで、利息を得る新しい資産運用の道が開けます。
デメリット(注意点):知っておくべきリスク
便利な一方で、以下のリスクも理解しておく必要があります。
- 信用リスク: 発行者であるJPYC株式会社が倒産した場合、価値が保証されなくなる可能性があります(ただし、日本の法律では利用者の資産は保全される仕組みになっています)。
- システムリスク: ハッキングやシステムのバグにより、資産を失う可能性はゼロではありません。
- デペッグリスク: 市場の混乱など、何らかの理由で1 JPYC ≠ 1円となり、価値が連動しなくなるリスクです。
JPYCとステーブルコインの将来性
JPYCの登場は、単なる新しい決済手段の追加に留まりません。日本の金融システム全体を変える可能性を秘めています。
私たちの生活への影響
将来的には、以下のようなユースケースが期待されています。
- 行政サービス: 税金や公共料金の支払いがJPYCで可能に。
- 給与のデジタル払い: 銀行口座を介さず、給与をJPYCで直接受け取れる未来も。
日本のステーブルコイン市場のこれから
JPYCの成功は、他の金融機関の参入を促しています。すでに三菱UFJ信託銀行や三井住友銀行なども円建てステーブルコインの発行を計画・検討しており、市場は今後ますます活性化していくでしょう。業界全体でデジタル通貨の実用化を目指す「デジタル通貨フォーラム」の動きも活発です。
結論:ステーブルコインの可能性を理解し、情報収集から始めよう
ここまで見てきたように、日本円ステーブルコイン「JPYC」は、私たちの生活やビジネスをより便利で効率的にする大きな可能性を持った金融インフラです。
もちろん、新しい技術であるためリスクも存在します。しかし、その仕組みと可能性を正しく理解することが、未来の金融サービスを使いこなすための第一歩です。
この記事を読んでJPYCやステーブルコインに興味を持った方は、まずは信頼できる国内の暗号資産取引所などで情報収集を続けてみてはいかがでしょうか。
【免責事項】
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。
FAQ(よくある質問)
Q1. JPYCはどこで購入できますか?
A1. 2025年秋以降、JPYCの公式サイト「JPYC EX」を通じて、銀行振込などで直接購入(発行)できるようになる予定です。常に「1 JPYC = 1円」のレートで購入できるのが特徴です。
Q2. JPYCを持つと税金はかかりますか?
A2. 日本円でJPYCを購入・保有しているだけでは、通常は課税対象になりません。しかし、JPYCを使って他の暗号資産を購入したり、JPYCを売却して利益が出たりした場合は、その利益が雑所得として課税対象になる可能性があります。詳しくは国税庁の最新情報を確認するか、税務の専門家にご相談ください。
Q3. JPYCは安全ですか?
A3. JPYCは、日本の資金決済法に準拠し、発行額と同額以上の日本円を準備金として保全する「法定通貨担保型」を採用しているため、他の仕組みのステーブルコインと比較して高い安全性を有しています。また、金融庁に登録された資金移動業者として、当局の監督下で運営されるため、信頼性も担保されています。ただし、発行者の信用リスクやシステムリスクがゼロではない点は理解しておく必要があります。

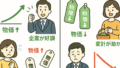
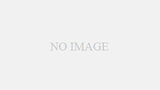
コメント