【2025年最新版】JEPQとJEPI、どっちを選ぶ?話題の高配当ETFを徹底比較!
「毎月分配金がもらえる高配当ETF」として、個人投資家の間で絶大な人気を誇るJEPIとJEPQ。あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
これらは、世界的な資産運用会社であるJ.P.モルガンが運用するETFで、高い分配金利回りを実現することを目指しています。特に、老後資金の準備や早期リタイア(FIRE)を目指す方々から、安定したキャッシュフローを生み出す資産として熱い視線が注がれています。
しかし、「名前は似ているけど何が違うの?」「自分にはどっちが合っているの?」といった疑問を持つ方も多いはずです。
この記事では、そんなあなたの疑問を解消するため、JEPQとJEPIの2つのETFを、基本的な仕組みからリスク、税金に至るまで徹底的に比較・解説します。この記事を最後まで読めば、あなたがどちらを選ぶべきか、明確な答えが見つかるはずです。
目次
JEPQとJEPIの共通点:高配当を生み出す「カバードコール戦略」
まず、JEPQとJEPIに共通する最大の特徴は「カバードコール戦略」という運用手法を用いている点です。
【💡超かんたん解説】カバードコール戦略とは?
- まず、普通に株式を保有します。
- その上で、「将来、あらかじめ決めた価格でその株を買う権利(コールオプション)」を他の投資家に売却します。
- この権利を売却することで「プレミアム」という手数料収入を得ることができます。
この「プレミアム収入」が、JEPQやJEPIの高い分配金の主要な源泉となっているのです。
ただし、この戦略には大きな特徴(トレードオフ)があります。
- メリット:株価が横ばい、または緩やかに下落する相場でも「プレミアム収入」によって利益を得やすい。
- デメリット:株価が権利行使価格を大きく超えて急騰した場合、その値上がり益は放棄することになるため、大きなリターンは狙えません。
つまり、大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を一部あきらめる代わりに、安定的(※)な現金収入(インカムゲイン)を狙う戦略と覚えておきましょう。
(※分配金額は保証されておらず、市場のボラティリティに応じて毎月変動します。)
【本題】JEPQとJEPIの決定的違いは「投資対象」
では、この2つのETFの最も大きな違いは何でしょうか?それは、カバードコール戦略の土台となる「投資対象の株式」です。
| 項目 | JEPI (J.P.モルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF) | JEPQ (J.P.モルガン・NASDAQ・プレミアム・インカムETF) |
|---|---|---|
| 主な投資対象 | S&P 500 構成銘柄(米国の優良企業500社) | NASDAQ 100 構成銘柄(米国の新興企業・ハイテク株100社) |
| 銘柄の傾向 | ディフェンシブ、低ボラティリティな割安株中心 | 成長性が高い大型グロース株、ハイテク企業中心 |
| 性格 | 安定志向のバランス型 | 成長志向のテクノロジー特化型 |
| 経費率 | 年率 0.35% | 年率 0.35% |
JEPI:S&P 500のディフェンシブ銘柄で安定感を重視
JEPIが投資するのは、S&P 500を構成する銘柄の中から、さらに独自の基準で選別した「ディフェンシブ」で「割安」な株式です。S&P 500は、米国経済を代表する優良企業500社で構成される、非常に分散の効いた指数です。JEPIは、その中でも特に値動きが比較的穏やか(低ボラティリティ)な銘柄に投資することで、市場全体が下落する局面での耐性を高めることを目指しています。
JEPQ:NASDAQ 100の成長株でより高いリターンを狙う
一方、JEPQが投資するのは、米国のハイテク・IT企業が多くを占めるNASDAQ 100の構成銘柄が中心です。NASDAQ 100は、NVIDIA、Microsoft、Appleといった世界をリードする巨大テクノロジー企業が名を連ねています。これらの企業は成長期待が高い反面、株価の変動(ボラティリティ)が大きくなる傾向があります。JEPQは、テクノロジーセクターの成長を取り込みつつ、カバードコール戦略でインカムも得るという、JEPIよりもやや積極的な運用を目指すETFと言えます。
パフォーマンスとリスクを徹底比較!
トータルリターン比較:上昇相場ではインデックスに軍配
トータルリターン(値上がり益+分配金)で比較すると、強い上昇相場では、カバードコール戦略の「上昇益が限定される」というデメリットが影響し、どちらのETFも対象インデックスに劣後する傾向が見られます。
- 2023年の上昇相場: QQQ (NASDAQ 100 ETF) が+55%のリターンを記録した一方、JEPQのリターンは30%台半ばに留まりました。
- JEPIとS&P 500の比較: JEPIは設定された2020年5月以降、市場が下落した2022年を除き、毎年S&P 500のトータルリターンを下回っています。
これは、高い分配金が株価の成長を犠牲にしている側面があることを示しています。
分配金利回り比較:どちらも非常に高い水準
分配金の利回りは、両ETFの最大の魅力です。
- JEPI: SEC利回り 8.62% (2025年7月16日時点)
- JEPQ: SEC利回り 11.24% (2025年7月28日時点)
米国10年債の利回りが4.20%程度、S&P 500の配当利回りが1.30%程度であることと比較すると、いかにこの利回りが高いかが分かります。
リスク(値動きの大きさ)比較:JEPIの安定感が光る
リスクの観点では、JEPIの下落耐性の強さがデータで示されています。
| 指標 | JEPI | JEPQ | S&P 500 (SPY) | NASDAQ 100 (QQQ) |
|---|---|---|---|---|
| ボラティリティ (標準偏差) | 9.15% | 14.20% | 17.00% | 16.19% |
| 最大ドローダウン (最大下落率) | 約 -13.71% | 約 -20.6% | 約 -24.50% | 約 -32.6% |
注目すべきはJEPIの低ボラティリティと下落率の小ささです。市場の急落時に損失を抑える効果が期待できます。JEPQもNASDAQ 100よりはリスクが抑えられていますが、元の指数の特性を反映し、JEPIよりは値動きが荒いことが分かります。
結論:あなたに合うのはJEPQ?それともJEPI?
👨👩👧👦 JEPIがおすすめな人
- とにかく安定したインカムを重視したい方
- 市場の大きな下落に対するリスクをできるだけ抑えたい保守的な方
- 退職後の生活資金など、定期的なキャッシュフローを確保したい方
- ポートフォリオの守りの部分を固めたい方
🚀 JEPQがおすすめな人
- テクノロジー企業の成長にも期待しつつ、高いインカムも欲しい方
- JEPIよりは高いリスクを取れる、やや積極的な方
- NASDAQ 100への投資に魅力を感じているが、ボラティリティは少し抑えたい方
- ポートフォリオに成長性とインカムの両方の要素を加えたい方
よくある質問(FAQ)
Q1. 日本で投資する場合、税金はどうなりますか?
A. 2025年8月現在、JEPQとJEPIは日本の新NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)の対象外です。そのため、これらのETFに投資する場合、通常は特定口座や一般口座で取引することになります。
税金の仕組みは少し複雑です。
- まず、米国ETFの分配金には、現地アメリカで10%の税金が源泉徴収されます。
- 次に、アメリカで税引きされた後の金額に対し、日本国内でさらに約20%(所得税+住民税)が課税されます。
つまり、何もしないと二重で税金がかかってしまいます。しかし、この二重課税を調整するために「外国税額控除」という制度があります。確定申告でこの手続きを行うことで、アメリカで支払った税金分を、日本の所得税や住民税から差し引く(還付を受ける)ことが可能です。手続きの手間はかかりますが、実質的な手取り額を増やすために非常に重要な制度です。
Q2. 分配金は税務上、不利だと聞きましたが?
A. はい、その可能性があります。カバードコール戦略で得られるプレミアム収入は、税務効率が低い傾向があります。モーニングスター社のデータによると、JEPIの3年間の税コスト比率は3.55%と報告されており、リターンのかなりの部分が税金で目減りする可能性を示唆しています。課税口座で保有する場合、この税負担は複利効果を損なう要因となるため、税引き後の実質リターンを常に意識することが重要です。
Q3. JEPIやJEPQだけで資産形成するのは危険ですか?
A. 資産形成の「コア(中核)」とすることには注意が必要です。なぜなら、長期的なトータルリターンでは、S&P 500やNASDAQ 100に連動する低コストのインデックスファンドに劣後する可能性が高いからです。あくまでポートフォリオの「サテライト(衛星)」として、インカム向上やリスク分散の目的で一部を組み入れるのが賢明な活用法と言えるでしょう。
まとめ
今回は、人気の高配当ETFであるJEPQとJEPIを徹底比較しました。
- 共通点: カバードコール戦略で高いインカムを生み出す。
- 相違点: JEPIはS&P 500の安定株、JEPQはNASDAQ 100の成長株に投資。
- リスク: JEPIの方が低リスクで下落に強い傾向があります。
- リターン: 上昇相場でのトータルリターンは、どちらもインデックスに劣後する傾向があります。
最終的にどちらを選ぶべきかは、あなたの「リスク許容度」と「投資目標(インカム重視か、成長も期待するか)」次第です。今回の記事を参考に、ご自身の投資スタイルに合ったETFを選び、賢い資産運用の一歩を踏み出してください。
【免責事項】
本記事は投資に関する情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。本記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


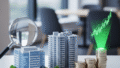
コメント