
この記事の目次
はじめに:その投資、「なんとなく」で選んでいませんか?
こんにちは!投資歴5年の個人投資家です。2024年から始まった新NISAをきっかけに、周りでも投資を始める友人が増えてきました。
特に、NISAの買付ランキングで常に上位にいる「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(通称:オルカン)。この2つは、まさに鉄板ですよね。
何を隠そう、投資を始めたばかりの僕も「みんなが買っているから」「人気だから」という理由で、深く考えずに積立設定をしていました。しかし、5年間投資を学び、実践してきて思うのは、「なぜそのファンドを選ぶのか」を自分の言葉で説明できることが、長期投資を続ける上で何よりも大切だということです。
この記事では、専門家のような難しい話は抜きにして、同じ個人投資家の目線から、この2つのファンドの「設計思想」や「本質的な違い」を徹底的に深掘りしていきます。この記事を読めば、あなたがどちらのファンドを選ぶべきか、きっと明確な根拠を持って判断できるようになるはずです。
S&P500とオルカンの基本情報を比較
まずは、両ファンドの基本スペックを表で比較してみましょう。ここを見るだけでも、大まかな違いが掴めます。
| 比較項目 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント | 三菱UFJアセットマネジメント |
| ベンチマーク | S&P500指数 | MSCI ACWI(オール・カントリー・ワールド・インデックス) |
| 投資対象国 | 米国のみ | 全世界(先進国23、新興国24) |
| 組入銘柄数 | 約500社 | 約2,900銘柄 |
| 信託報酬(年率) | 0.09372%以内 | 0.05775%以内 |
| 総経費率(年率) | 約0.10% | 約0.11% |
【実績比較】リターンとリスクを徹底分析
次に、僕たち投資家が最も気になるであろう過去の実績を比較します。
過去のリターン比較
| 期間 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
|---|---|---|
| 年初来 | +15.94% | +15.79% |
| 3年(年率) | +21.62% | +20.03% |
| 10年(年率) | +24.38% | +21.31% |
※2025年8月22日時点のデータ
過去の実績を見ると、いずれの期間においてもS&P500がオルカンを上回るリターンを上げています。これは、近年の米国経済、特に巨大テクノロジー企業の目覚ましい成長が大きく影響しています。
リスク(価格の振れ幅)の比較
一般的に、投資対象が広いオルカンの方が、理論上はリスク分散が効いています。米国経済が不調に陥った際、他の国の成長がカバーしてくれる可能性があるためです。
しかし、注意点があります。オルカンの構成国の約6割は米国であり、値動きがS&P500と非常に似通う傾向にあります。そのため、世界的な金融危機などで米国株が大きく下落する局面では、期待するほどのリスク低減効果が得られない可能性も理解しておく必要があります。
ベンチマークを深掘り!指数の「設計思想」と仕組み
さて、ここからはこの記事の核心部分です。両ファンドのパフォーマンスの源泉となっているベンチマーク(目標とする指数)について、その「設計思想」や「仕組み」を詳しく見ていきましょう。
そもそも「ベンチマーク」とは、投資信託が運用の目標とする指標のことです。インデックスファンドは、このベンチマークと全く同じ値動きをすることを目指して運用されます。つまり、ベンチマークを理解することこそが、ファンドを理解する上で最も重要なのです。
S&P500:「質」を重視するエリート集団
S&P500が連動を目指す「S&P500指数」は、単に米国の時価総額上位500社を集めたものではありません。採用されるには、以下のような厳しい基準をクリアする必要があります。
- 米国企業であること
- 時価総額が一定以上であること
- 四半期利益が4四半期連続で黒字であること
- 高い流動性(売買のしやすさ)があること
特に注目すべきは「4四半期連続黒字」という利益基準です。これは、いわば学校のクラスの中から、ただ体が大きい生徒を選ぶのではなく、「成績も優秀(利益が出ている)で、人気者(取引が活発)な優等生」だけを厳選するようなものです。
このように、S&P500は利益という「質」を重視して優良企業に偏るように設計されています。この仕組みこそが、S&P500が歴史的に高いリターンを上げてきた本質的な理由だと僕は考えています。
▼ セクター構成比と”新陳代謝”の仕組み
さらに、S&P500の構造を理解する上で重要なのが、セクター(業種)別の構成比率です。
| セクター | 構成比率(約) | 主な企業例 |
|---|---|---|
| 情報技術 | 31.6% | アップル、マイクロソフト、エヌビディア |
| 金融 | 14.3% | バークシャー・ハサウェイ、JPモルガン |
| ヘルスケア | 9.6% | イーライリリー、ジョンソン&ジョンソン |
| 一般消費財 | 10.6% | アマゾン、テスラ、ホームデポ |
| コミュニケーション | 9.6% | グーグル(アルファベット)、メタ |
| 生活必需品 | 5.9% | P&G、コストコ、コカ・コーラ |
| 資本財 | 8.7% | GE、ボーイング、キャタピラー |
| エネルギー | 3.0% | エクソンモービル、シェブロン |
| 不動産 | 2.1% | プロロジス、アメリカン・タワー |
| 公益事業 | 2.5% | ネクステラ・エナジー、デューク・エナジー |
| 素材 | 1.9% | リンデ、エア・プロダクツ |
※2025年5月30日時点のデータ
このように、情報技術セクターが全体の約3割を占めており、近年の米国株の成長を牽引してきた巨大テック企業への投資比重が高いことがわかります。
また、S&P500は四半期に一度、構成銘柄の定期的な見直し(リバランス)を行っています。これにより、業績が悪化して基準を満たさなくなった企業は除外され、新たに成長してきた優良企業が採用されます。この常にエリートであり続けるための”新陳代謝”こそが、S&P500が長期的に高いパフォーマンスを維持してきた秘訣の一つなのです。
オルカン(MSCI ACWI):「量」を重視する世界市場の縮図
一方、オルカンが連動を目指す「MSCI ACWI」は、特定の企業の「質」を問うのではなく、世界の株式市場の時価総額構成比を忠実に再現することを目的としています。
これは「時価総額加重平均」という方法で算出されており、簡単に言うと「会社の規模(時価総額)が大きいほど、指数全体に与える影響が大きくなる仕組み」です。だからこそ、オルカンの上位銘柄にはアップルやマイクロソフトといった世界的な大企業が名を連ねるのです。
▼ 国・地域別構成比と「自動調整機能」
オルカンの特徴を最もよく表しているのが、国・地域別の構成比率です。
- 米国:約60%
- 日本:約6%
- イギリス:約4%
- その他先進国:約20%
- 新興国:約10%
この比率は固定ではなく、MSCI ACWIも定期的に構成比率の見直しを行っています。これにより、例えば将来インドや他の新興国の経済が大きく成長し、世界の株式市場に占める割合が増えれば、自動的にそれらの国への投資比率が高まります。
僕たち投資家が将来を予測しなくても、指数が自動で世界の成長の中心に投資先を調整してくれる。これがオルカンの最大の魅力である「自動調整機能」の正体です。手間をかけずに、世界経済の成長の果実をまるごと受け取りたいと考える人にとって、非常に合理的な仕組みと言えるでしょう。
中身を拝見!上位構成銘柄とその共通点
両ファンドの具体的な組入上位銘柄を見てみると、興味深い事実がわかります。
| 順位 | S&P500 上位10銘柄 | オルカン(MSCI ACWI) 上位10銘柄 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 2 | アップル | アップル |
| 3 | エヌビディア | エヌビディア |
| 4 | アマゾン・ドット・コム | アマゾン・ドット・コム |
| 5 | メタ・プラットフォームズ | メタ・プラットフォームズ |
| 6 | アルファベット(クラスA) | アルファベット |
| 7 | アルファベット(クラスC) | ブロードコム |
| 8 | バークシャー・ハサウェイ | テスラ |
| 9 | イーライリリー | エリリリー |
| 10 | J.P.モルガン・チェース | アルファベット(C) |
※出典:S&P500は2024年5月31日時点、オルカンは2024年2月末時点のデータ
ご覧の通り、上位銘柄のほとんどが重複しており、いずれも米国の巨大テクノロジー企業が独占しています。
ただし、集中度には差があります。S&P500では上位10社の比率が約34%に達するのに対し、オルカンでは約20%に留まります。これは、S&P500の方が特定企業への依存度が高く、これらの企業の業績がファンド全体に与える影響が大きいことを意味しています。
メリット・デメリットを整理!各ファンドの特徴まとめ
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| S&P500 | ・歴史的に高いリターンが期待できる ・「優良企業」に厳選投資できる ・情報が多く、馴染みのある企業が多い |
・米国一国への集中リスク ・米国経済が停滞した場合、大きな影響を受ける ・為替リスク(対ドル) |
| オルカン | ・究極の分散投資でリスクを低減できる ・将来の成長国を取り逃さない ・自動リバランス機能で手間いらず |
・リターンがS&P500に劣後する可能性がある ・結局、米国への依存度が高い(約6割) ・為替リスク(対複数通貨) |
結局どっち?あなたに合ったファンドの選び方
それでは、最終的にどちらのファンドを選べば良いのでしょうか。あなたの投資に対する考え方によって、最適な答えは異なります。
こんな人には「S&P500」がおすすめ
- 今後も米国が世界経済を牽引し続けると強く信じている人
- リスクを取ってでも、より高いリターンを積極的に狙いたい人
- 分散性よりも、投資対象の「質」の高さを重視する人
こんな人には「オルカン」がおすすめ
- 将来どの国が成長するか予測するのは難しい(したくない)と考える人
- とにかく手間をかけずに、世界全体にまるごと分散投資したい人
- 大きなリターンよりも、リスクを抑えた安定的な資産形成を最優先したい人
「両方買う」のはアリ?僕個人の考え
「S&P500の成長力も捨てがたいし、オルカンの分散力も魅力的…。うーん、どっちか一つになんて絞れない!」
投資を始めた頃の僕も、全く同じことで悩みました。そこで、僕個人の考えを正直にお伝えすると、「そんなに悩むくらいなら、いっそ両方買ってしまうのもアリ」だと思っています。
悩んでしまって投資を始められないのが、一番もったいないからです。まずは少額からでも両方を積み立ててみて、「あっちにしておけば良かった…」という後悔を減らすのも、投資を長く続けるコツの一つかもしれません。
ただし、これはあくまで「悩みを解決する」ための一つの手段です。投資の基本である「リスク分散」という観点から見ると、話は少し変わります。
前述の通り、S&P500とオルカンは中身の多くが重複しているため、両者を組み合わせても期待するほどのリスク低減効果は見込めません。もしあなたが、株式市場全体が下落するような局面でも資産の目減りを抑えたい、つまり本質的な意味での分散を考えるなら、株式とは異なる値動きをする資産、例えばゴールド(金)やリート(不動産投資信託)、債券などをポートフォリオに加える方が、ずっと効果的です。
まとめると、「悩んで動けないなら両方買いもOK。でも、本当のリスク分散をしたいなら、株以外の資産も検討しよう!」ということですね。
まとめ:自分だけの「正解」を見つけよう
S&P500とオルカン。両者は単なる「米国か、全世界か」という違いだけでなく、
- S&P500:選ばれし優良企業に集中投資する「質」の戦略
- オルカン:世界市場全体をまるごと買う「量」の戦略
という、根本的な設計思想の違いがあることをご理解いただけたかと思います。
どちらも長期的な資産形成のツールとして非常に優れていることは間違いありません。大切なのは、周りの意見や目先のリターンに惑わされず、自分の投資目的やリスク許容度、そして世界経済に対する考え方と照らし合わせ、納得のいく一本を選ぶことです。
個人的にはどちらのファンドを選ぶかというより少額でも良いので長期的に積立分散投資をすることが安定したリターンを得るのに重要だと考えています。
専門家の意見ももちろん参考になりますが、最後に決めるのは自分自身。この記事が、あなたが後悔しないファンド選びをするための、一つの判断材料となれば嬉しいです。
よくある質問(FAQ)
Q1: S&P500とオルカン、途中で切り替えるのはアリですか?
A1: はい、可能です。ただし、売却して利益が出た場合は課税対象となるため注意が必要です(NISAの非課税保有限度額内での売却・再投資は非課税です)。ご自身の相場観やライフプランの変化に応じて見直すのは良い選択肢ですが、短期的な市場の変動で頻繁に売買することは個人的には推奨しません。
Q2: 新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で、どう使い分けるのが良いですか?
A2: 最もシンプルなのは、両方の枠で同じファンド(S&P500またはオルカン)を積み立てる方法です。もし使い分けるのであれば、コア(中核)となる資産を「つみたて投資枠」でオルカンに、サテライト(補完)としてより高い成長を期待する部分を「成長投資枠」でS&P500に、といった考え方もあります。ただし、管理が複雑になる点にはご留意ください。
Q3: 為替リスクはどちらのファンドにもありますか?
A3: はい、どちらのファンドも海外の資産に投資するため、為替変動の影響を受けます。S&P500は米ドル、オルカンは米ドルを中心に様々な通貨の影響を受けます。円高になれば基準価額の下落要因、円安になれば上昇要因となります。これは海外投資において避けられないリスクですが、長期的に見れば平準化される傾向にあると僕は考えています。
投資に関するご注意
- 本記事は一個人の見解や情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。
- 投資信託は価格変動リスクや為替変動リスクなどを伴い、元本が保証されているものではありません。
- 投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。


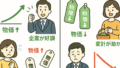
コメント