
日本の貯蓄、平均はホント? 年代別のリアルな貯蓄額と格差が生まれるワケ
「みんなどのくらい貯蓄しているんだろう?」と、気になったことはありませんか。ニュースなどで「平均貯蓄額〇〇万円」という数字を見て、驚いたり、焦ったりすることもあるかもしれません。
しかし、その「平均値」は、必ずしも実態を正確に表しているとは言えません。よりリアルな姿を映し出す「中央値」と比較し、なぜ日本で貯蓄格差が生まれているのか、その構造的な理由を分かりやすく解説します。
目次
「平均値」と「中央値」で見る、年代別の貯蓄リアル
まず、平均値と中央値の違いを簡単に説明します。
- 平均値: 全員の貯蓄額を合計し、人数で割ったもの。一部の極端に貯蓄額が多い「富裕層」がいると、その金額に大きく引き上げられてしまいます。
- 中央値: 貯蓄額を少ない順に並べたとき、ちょうど真ん中に来る人の値。こちらの方が、より「普通」の感覚に近いと言えます。
下の表は、金融資産を保有している世帯の年代別データです。平均値と中央値の間に、どれほどの差があるか見てみましょう。
| 世帯主の年齢 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 266万円 | 120万円 |
| 30歳代 | 874万円 | 315万円 |
| 40歳代 | 1,181万円 | 500万円 |
| 50歳代 | 1,773万円 | 700万円 |
| 60歳代 | 2,499万円 | 1,200万円 |
データを見ると、どの年代でも平均値が中央値を大きく上回っていることが分かります。特に60代では、平均値が約2,500万円なのに対し、中央値は1,200万円と、倍以上の開きがあります。
これは、ごく少数の富裕層が平均値を大きく引き上げている一方で、多くの世帯の貯蓄額は平均よりもはるかに少ないという「富の偏在」が起きていることを示しています。 そしてこの差は、年齢が上がるにつれて拡大する傾向にあります。
なぜ貯蓄格差は生まれるのか?3つの大きな要因
では、なぜこれほどの貯蓄格差が生まれてしまうのでしょうか。その背景には、複雑に絡み合った複数の要因があります。
1. 収入の格差(所得格差)
貯蓄格差の最も根本的な原因は、収入の格差です。
- 非正規雇用の増加: 正規雇用と比べて賃金が低く、雇用も不安定な非正規雇用者が増えたことで、所得格差が拡大しました。 非正規雇用者の生涯賃金は、正規雇用者の半分程度になることもあると指摘されています。
- 貯蓄率の違い: 高所得層ほど収入に占める貯蓄の割合(貯蓄率)が高い傾向にあります。 収入が低いと生活費で手一杯になり、貯蓄に回す余裕が生まれにくいため、所得の差が時間とともにより大きな資産の差となって表れます。
2. 資産価格の変動
近年の株価上昇なども、格差を広げる一因となっています。
- 金融資産ポートフォリオの違い: 富裕層は、資産の中に株式や投資信託といった「リスク性資産」を多く保有する傾向があります。
- 株価上昇の恩恵: 昨今の株価上昇は、こうしたリスク性資産を持つ層の資産を大きく増やしました。 一方で、預貯金が中心の層はその恩恵を受けにくく、資産を持つ者と持たざる者の差がさらに開く結果となっています。
3. ライフステージと世代間の課題
人口構造の変化も、格差に影響を与えています。
- 高齢者の貯蓄温存: 日本の高齢者は、将来の医療や介護への不安から、想定されているほど資産を取り崩さない傾向があります。 資産を持つ高齢者が富を維持する一方で、貯蓄の少ない高齢者が生活に困窮するという「世代内格差」が深刻化しています。
- 若年層の資産形成の困難: 今の若者世代は、賃金が上がらず、低金利が続く中で資産を形成するという、過去の世代より厳しい状況に置かれています。 若者の中でも、NISAなどを活用して投資を行う層と行わない層とで、将来の資産に差が生まれる可能性が指摘されています。
まとめ
日本の貯蓄の実態を見ると、「平均値」は一部の富裕層によって引き上げられており、「中央値」の方がより一般的な状況を反映していると言えます。 そして、その二つの数値の乖離は、日本社会に存在する大きな貯蓄格差を示しています。
この格差は、「所得格差」「資産価格の変動」「世代間の課題」といった要因が複雑に絡み合って生まれています。
こうした現実を理解することは、周りと比べて一喜一憂するためではなく、自分自身のライフプランや資産形成を冷静に考えるための第一歩となるでしょう。

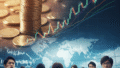
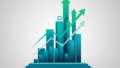
コメント